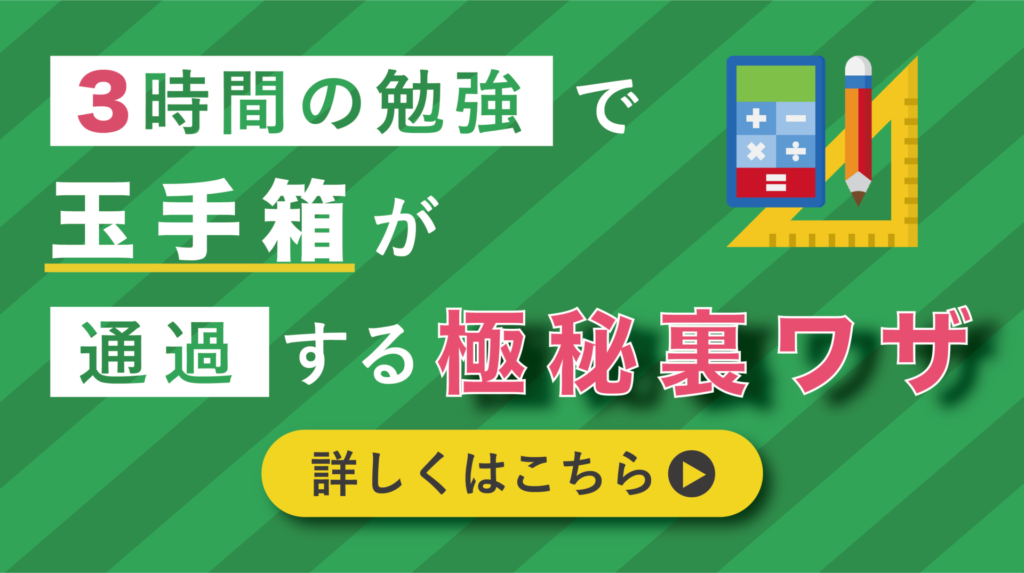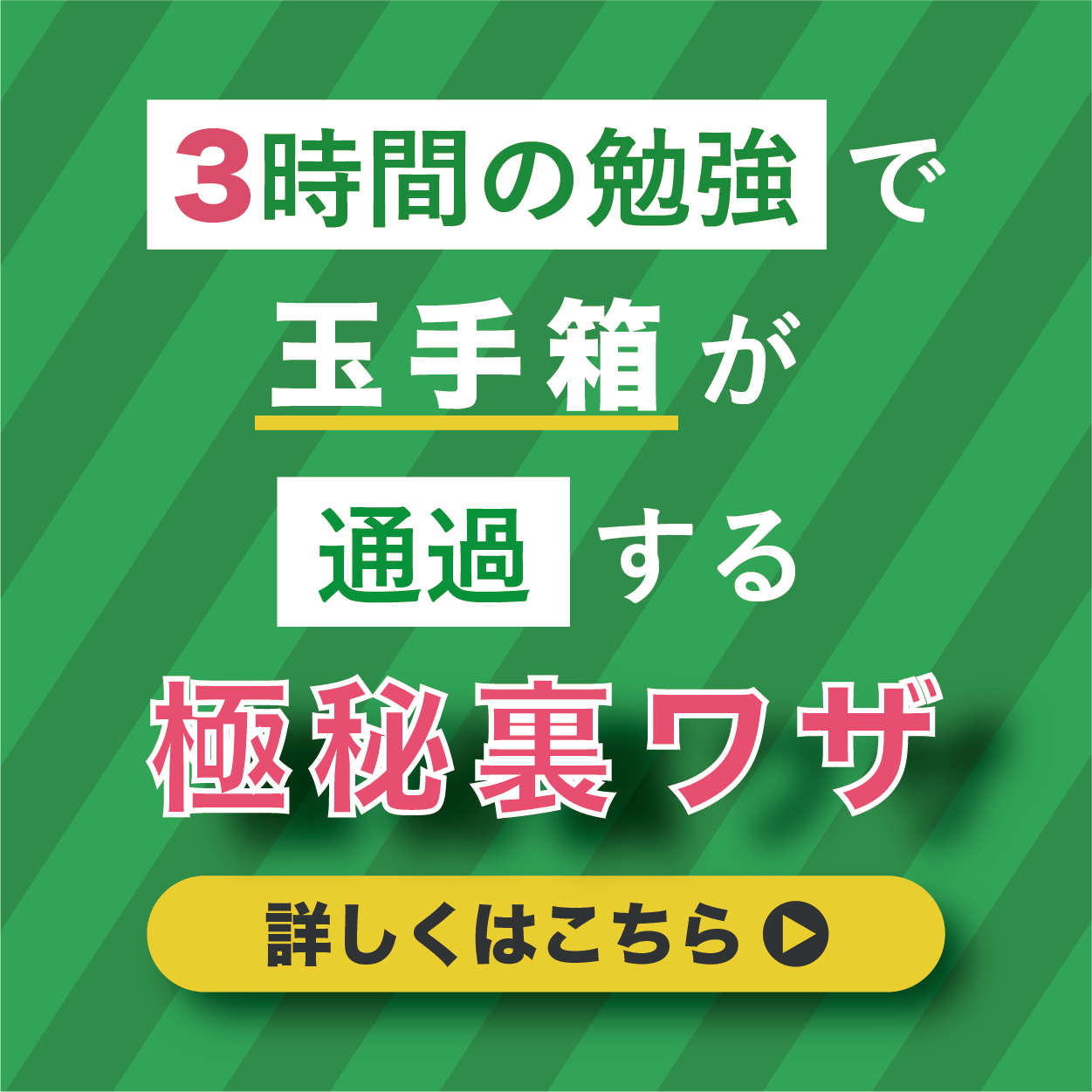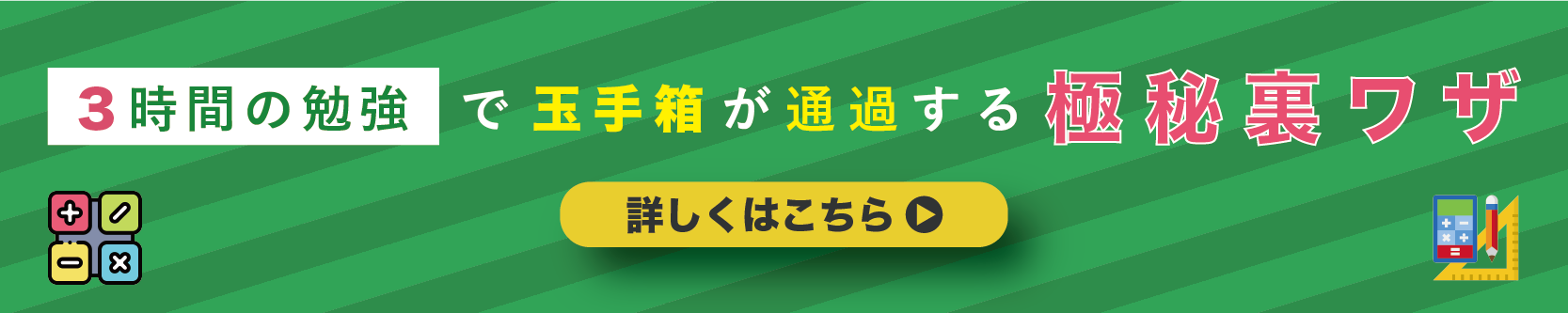玉手箱は数多くあるWEBテスト(適性検査)の中でも比較的難しい方なので、十分な勉強・対策が必要です。
※「玉手箱とは?対策方法や試験の特徴は?対策いらない?完全解説で就活生・社会人必見!」もぜひ参考にしてください。
後ほど詳しく解説しますが、玉手箱の勉強時間としては60時間程度は確保したいところです。
本記事では玉手箱を今までに100回以上受検し、日本トップクラスに玉手箱を知り尽くしている私アキラが、玉手箱の勉強時間の目安(60時間)と具体的なスケジュールをご紹介していきます。
玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人はぜひ参考にしてください。
ちなみにですが、玉手箱にはたった3時間の勉強で玉手箱が通過してしまう勉強法があります。
これさえあれば60時間も勉強する必要はありません。限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。
これは私が100回以上もの玉手箱受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。
玉手箱の勉強時間は60時間が目安
本記事のタイトルと冒頭でも解説した通り、玉手箱を本気で対策したいのであれば、勉強時間としては最低でも60時間程度は確保したいところです。
60時間というと、1日2時間玉手箱の勉強をする場合、30日かかります。
つまり、勉強時間=60時間というのは目安としては1ヶ月程度になります。
玉手箱の対策にそれくらいの時間がかかる理由としては主に以下の3つです。
- 出題範囲が広いから
- 問題を解くスピードを上げる必要があるから
- 表の空欄の推測の対策をする必要があるから
それぞれ詳しく解説していきます。
出題範囲が広いから
玉手箱の出題範囲(科目)と試験時間・問題数は以下の通りとなっており、非常に幅広いです。
| 科目 | 試験時間 | 問題数 |
|---|---|---|
| 論理的読解(言語) | 25分または15分 | 52問または32問 |
| 趣旨判断(言語) | 10分 | 32問 |
| 趣旨把握(言語) | 12分 | 10問 |
| 四則逆算(計数) | 9分 | 50問 |
| 図表の読み取り(計数) | 35分または15分 | 40問または29問 |
| 表の空欄の推測(計数) | 35分または20分 | 35問または20問 |
| 論理的読解(英語) | 10分 | 24問 |
| 長文読解(英語) | 10分 | 24問 |
| パーソナリティ(性格検査・正式版) | 約20分 | 68問 |
| パーソナリティ(性格検査・簡易版) | 特になし | 30問 |
| 意欲(性格検査・正式版) | 約15分 | 36問 |
| 意欲(性格検査・簡易版) | 特になし | 36問または48問 |
※詳しくは「玉手箱の所要・試験時間と問題数を科目別に解説!サンプル問題付き」をご覧ください。
玉手箱を選考フローに導入している多くの企業は
- 論理的読解+図表の読み取り+性格検査
- 論理的読解+表の空欄の推測+性格検査
- 趣旨判断+四則逆算+性格検査
の組み合わせを採用していますが、どの科目が出題されるかは玉手箱の受検案内が企業から送られてくるまではわかりませんので、それまでは上記の科目を幅広く勉強する必要があります。
※言語の趣旨把握と英語を出題する企業はほとんどありませんので、対策の優先順位は下げて問題ありません。
※「玉手箱の性格検査・パーソナリティとは?落ちる?時間は20分?例題や問題内容を無料で紹介」もぜひ合わせてご覧ください。
問題を解くスピードを上げる必要があるから
玉手箱が難しいWEBテスト(適性検査)と言われている理由は上記の表をご覧いただくと分かる通り、問題数に対して試験時間がかなり短いからです。
※「玉手箱は難しいので要注意!3時間の勉強で通過する極秘裏ワザをご紹介」もぜひ合わせてご覧ください。
特に四則逆算に関しては試験時間=9分で問題数=50問なので、すべての問題を解こうと思うと、単純計算で1問あたり約10秒のペースで回答しなければなりません。
初めて玉手箱を受検する人は試験時間の短さに苦戦してしまうケースが多いので、対策段階から問題を解くスピードを上げることを意識しなければなりません。
問題を解くスピードを上げるためにはある程度時間をかけて玉手箱の勉強・対策をする必要があります。一朝一夕で身に付くものではないということを心がけておきましょう。
表の空欄の推測の対策をする必要があるから
上記の表の通り、玉手箱の計数では表の空欄の推測という科目が出題される可能性があります。
※「玉手箱の計数理解(非言語・数学)のコツ!終わらない人続出?例題・練習問題と解答付き!」もぜひ参考にしてください。
表の空欄の推測はかなり特殊な問題で、ある程度解き方を知っていないと苦戦するケースが多いです。
例題は以下の通りです。
※「玉手箱の問題・例題を全科目紹介!練習問題も無料!どんな問題か知りたい人必見」もぜひ参考にしてください。
【例題】
あるスーパーマーケットが、果物の仕入数をまとめています。
<曜日別仕入数>
| 単位:個 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| メロン | 156 | 97 | 131 | 171 | ? |
| ミカン | 67 | 67 | 54 | 65 | 103 |
| リンゴ | 41 | 55 | 38 | 13 | 34 |
| ブドウ | 16 | 61 | 57 | 31 | 45 |
金曜日のメロンの仕入数は何個と推測できるか。
- 98個
- 105個
- 116個
- 122個
- 141個
【解答&解説】
月曜日〜木曜日における各果物の仕入数の合計は以下の通りです。
- 月曜日:156+67+41+16=280[個]
- 火曜日:97+67+55+61=280[個]
- 水曜日:131+54+38+57=280[個]
- 木曜日:171+65+13+31=280[個]
よって、金曜日の仕入数の合計も280個になると推測できるので、答えは280-(103+34+45)=98[個]・・・(答)となります。
後ほど詳しく解説しますが、玉手箱の表の空欄の推測には全部で7個のパターンが存在するので、しっかりと対策をしようと思うとそれなりの勉強時間を必要とします。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
玉手箱の勉強時間60時間の具体的スケジュール
ここからは、勉強時間=60時間で
- 論理的読解(15時間)
- 趣旨判断(3時間)
- 四則逆算(3時間)
- 図表の読み取り(15時間)
- 表の空欄の推測(20時間)
- 模擬試験(4時間)
の5科目を対策するための具体的スケジュールをご紹介していきます。
現在は書店やAmazonなどで数多くの玉手箱の問題集が販売されているので、自分に合った問題集を購入して対策を進めていきましょう。
勉強時間=60時間が確保できる場合、そこそこページ数が多くて問題数も豊富な問題集を購入することをおすすめします。
そんな問題集の中で筆者のおすすめは大和書房から出版されている『Webテスト 最強問題集』です。
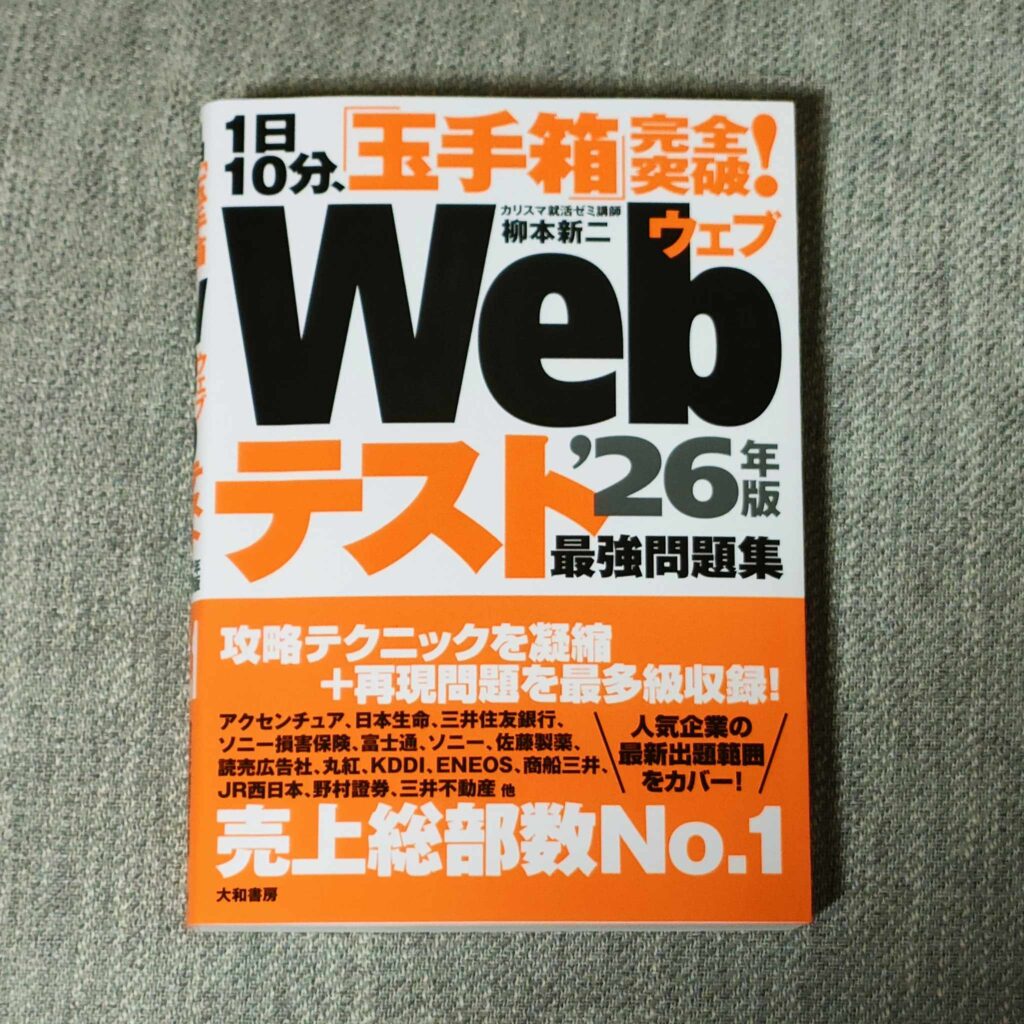
上記の通り筆者も実際に購入してみましたが、ページ数は全部で319ページあり、問題数も玉手箱の問題集の中ではトップクラスに多く掲載されています。
解答・解説も丁寧なので、学力にあまり自信がない人でも取りかかりやすい問題集だと思います。
料金は税込1,650円です。玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人はぜひ購入を検討してみてください。
※「玉手箱の対策本・問題集・参考書を全冊紹介!ダウンロードできる?おすすめは?ランキングも!」という記事もぜひ合わせてご覧ください。
論理的読解(15時間)
まずは15時間程度の勉強時間を言語の論理的読解に使いましょう。
※「玉手箱の言語のコツは?練習問題・解答も!おかしい・難しいという声もご紹介」もぜひ参考にしてください。
論理的読解は多くの企業が導入している科目なので、対策の優先順位は高めです。
例題は以下の通りです。
【例題】
次の文章を読み、各設問文についてA、B、Cのいずれかにあたるか答えなさい。
中世に最盛期を迎えたキリスト教文化は、学問や絵画、建築など生活様式から形成物群に至るまで広く影 を及ぼしました。そして、その文化を生み出したキリスト教は、当時のみならず現在に至るまで、ヨーロッパ文化を支えるバックボーンとなっているのです。それなら「キリスト教徒でない人には、それらの文化や美術作品を本当に理解することはできないのでは?」と、疑問を抱く人がいるかもしれません。でも私は、そうは思いません。キリスト教についての基礎知識があれば、キリスト教徒でなくてもその文化や美術を味わい、理解できるはずだからです。そうでないと、世界中の人々が魅了される古代ギリシャ彫刻の人体美は、ゼウスなど神話の神々を信仰しなければ理解不能ということになってしまいます。
とはいうものの、ギリシャ神話は古代ギリシャ美術をおもしろく鑑賞するために欠かせません。同様に、キリスト教美術をより深く理解するためには、「受胎告知」や「東方の三博士」など、基礎的な知識は必要でしよう。知らなければ勝手な思い違いをしてしまうこともあります。
たとえば、川で洗濯しているおばあさんの前に巨大な桃が流れてくる絵を見れば、日本人なら誰でも昔話の「桃太郎」の一場面だとわかります。しかし、この話を知らない外国人はどう思うでしようか。 愉快そうだとか、 奇想天外な絵だとか、様々に思うにしても、その後のストーリーを想像できないのは確実です。
キリスト教のことを知らないままヨーロッパの中世美術に接すれば、これと同じようなことになってしまうと考えられます。聖書でもイエスの伝記とされる「福音書」の部分なら分量もわずかですし、最近は漫画化されたものや美術作品の写真で解説された本も出版されています。ギリシャ神話のような物語の一つと思えば、聖書はおもしろい読み物になるでしよう。
出典:『史上最強 玉手箱&C-GAB 超実戦問題集』ナツメ社
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)宗教美術は、それを信じる人しか本当に理解することはできない。
(2)キリスト教についての知識があれば、ヨーロッパ中世美術の鑑賞において思い違いをしてしまうことを減らせるはずだ。
(3)キリスト教美術の作品は、当時の宗教観や文化を理解するための資料となる。
(4)昔話の「桃太郎」は日本人の誰もが知る神話のようなものである。
【解答&解説】
(1)正解はBです。本文に「それなら「キリスト教徒でない人には、それらの文化や美術作品を本当に理解することはできないのでは?」と、疑問を抱く人がいるかもしれません。でも私は、そうは思いません」という記述があります。
(2)正解はAです。本文に「キリスト教美術をより深く理解するためには、「受胎告知」や「東方の三博士」など、基礎的な知識は必要でしよう。知らなければ勝手な思い違いをしてしまうこともあります」と記載があります。
(3)正解はCです。設問文の内容は本文のどこにも記載がありません。
(4)正解はCです。(3)と同様に、設問文の内容は本文のどこにも記載がありません。
玉手箱の問題集で論理的読解の問題を解くときは、以下3つのポイントを意識しながら解くと、効率良く点数を上げることができます。
- 選択肢A〜Cの意味を事前に理解しておく
- 設問文を先に読む癖を付ける
- 時間を意識しながらわからない問題は勘で回答する
それぞれの詳細については「玉手箱の論理的読解のコツは?具体例で解説!練習問題付き」で解説しているので、ぜひご覧ください。
趣旨判断(3時間)
続いては言語の趣旨判断に3時間程度の勉強時間を使います。
趣旨判断は論理的読解と比較すると出題頻度は落ちるので、対策優先度を少し下げて問題ありません。
趣旨判断の例題は以下です。
【例題】
次の文章を読み、続く設問文についてそれぞれA、B、Cを判断して選びなさい。ただし、4つの設問文の中には、AとCにあてはまるものがいずれも1つ以上含まれています。
話が長いというのは、単に時間的な長さの問題だけでなく、「双方向のコミュニケーションが活発化しない」という状況でもあります。
応募者が一方的にくどくどと話し、面接担当者が質問や感想をはさむ余地がない。相手はあれもこれもと聞かされるうちにお腹いっぱいになってしまい、「それだけ話せば、もうこちらから聞くことないよね」 と、対話を放棄してしまうわけです。
しかし、やはり双方向の対話がないと、相手は「お互いに理解し合えた」という納得感を得られません。結果、「今回は縁がなかったということで・・・」となってしまいます。
会話のキャッチボールを増やすには、相手が「質問したくなる」ようにしましょう。何もかも話してしまうのではなく、ある程度ポイントを絞るのが、1つの手です。
たとえば「自己アピールをしてください」と言われたとします。そこで、こんなふうに答えたとしたらどうでしよう。
「成功も失敗もいろいろと積み重ねてきましたが、それを通じて6つの力を身に付けることができたと思います。そのうち、特に御社で活かせると思う2つの力についてお話ししたいと思います。それは〜」
おそらく相手は「どんな成功体験、失敗体験があるんだろう」「あとの4つのカとは何だろう」「なぜその2つを選んだのだろう」などと、興味がわいて質問したくなるのではないでしようか。
あからさまに「思わせぶり」な態度はマイナス印象につながりますが、アピールを小出しにするのはなかなか有効です。つまり、相手に「突っ込みどころ」を提供するというわけです。
出典:『Webテスト 最強問題集』大和書房
A:筆者の趣旨(もっとも伝えたいこと)が述べられている。
B:筆者はそのことに触れているが、趣旨ではない。
C:この文章とは関係ないことが述べられている。
(1)話が長くなるのは思いがうまくまとまっていないからである。
(2)面接官は話の長い人を嫌う傾向にある。
(3)面接官はたくさんの体験をしている人に興味を持つ。
(4)双方向のコミュニケーションには、ポイントを1つにして話のやり取りを増やすことである。
【解答&解説】
(1)正解はCです。「思いがうまくまとまっていないから」とは本文には書かれていません。
(2)正解はBです。第1〜2段落に、面接官が話の長い人を嫌う旨は書かれていますが、これは筆者の一番伝えたいことではありません。
(3)正解はCです。第7〜8段落に経験の話が書かれていますが、面接官が興味を持つのは、経験談を選んで話すという使い方に対してです。
(4)正解はAです。こちらの設問文の内容が、筆者が一番伝えたいことになります。
趣旨判断の対策として問題集の問題を解くときは、以下のポイントを意識してください。
- 長文の内容の大枠を捉えながら読む
- 比較的見つけやすいAとCが答えになる設問を探す(Aが答えとなるものは必ず1つ・Cが答えとなるものは最低1つある)
- 残った設問をBかCに振り分ける
また、長文を読むときは文末表現に注目しながら読むのもポイントです。
- 「〇〇だ」「〇〇である」などの断定表現
- 「〇〇だが」「しかし」などの逆接表現の後の文
上記の詳細は「玉手箱の趣旨判定のコツは?趣旨把握との違いも例題で解説」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
四則逆算(3時間)
四則逆算はこの後ご紹介する図表の読み取り・表の空欄の推測と比較すると出題頻度は落ちるので、趣旨判断と同じく勉強時間は3時間程度でも問題ありません。
四則逆算の例題は以下です。
【例題】
□に入る数字を、以下の選択肢の中から選びなさい。
7+5+9=□÷3
- 57
- 60
- 63
- 66
- 69
【解答&解説】
□=(7+5+9)×3=21×3=63・・・(答)となります。
四則逆算では上記のような計算問題がひたすら50問続きます。
※電卓と計算用紙の使用は認められています。詳しくは「玉手箱は電卓・計算機禁止?おすすめは?スマホ電卓はなし?自宅受検はあり?」をご覧ください。
計算スピードは一朝一夕で伸びるものではないので、玉手箱の対策にあまり勉強時間をかけられない人は、四則逆算で出題される以下5パターンの問題をあらかじめ把握しておきましょう。
- 整数
- 小数
- 分数
- パーセント(%)
- □が複数個存在
それぞれの詳細は「玉手箱の四則逆算・四則演算とは?練習問題とコツ!時間足りない人は?ボーダーは?」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
図表の読み取り(15時間)
図表の読み取りは多くの企業が導入している科目なので、対策の優先順位は高めです。
例題は以下の通りです。
【例題】
以下の表を見て問いに答えなさい。
<劇団Xの公演数、入場者数、売上高の推移>
| 公演開催場所数 | 公演数 | 入場者数 | 売上高[万円] | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 28 | 42 | 13,493 | 5,302 |
| 2011年 | 18 | 26 | 8,912 | 4,102 |
| 2012年 | 52 | 74 | 46,521 | 13,409 |
| 2013年 | 48 | 101 | 40,454 | 18,651 |
| 2014年 | 46 | 69 | 28,492 | 12,594 |
2013年の1公演あたりの売上高は、2011年に比べて何%増えたか。最も近いものを、以下の選択肢から1つ選びなさい。
- 10%
- 13%
- 15%
- 17%
- 20%
【解答&解説】
2011年の1公演あたりの売上高は4,102÷26≒158[万円]です。
同様に考えて、2013年の1公演あたりの売上高は18,651÷101≒185[万円]です。
よって、増加率は(185÷158-1)×100=17.08・・・となるので、正解は17%・・・(答)です。
※増加率の計算方法がわからない人は「玉手箱で増加率・伸び率の求め方は必須知識!利用シーンをご紹介」をご覧ください。
玉手箱の問題集で図表の読み取りの問題を解くときは、以下3つのポイントを意識しながら解くようにしてください。
- わからない問題は時間をかけずに勘で回答する
- 余計な情報に惑わされないようにする
- 問題を解くために必要な公式を覚える
それぞれの詳細は「玉手箱の図表の読み取りとは?ボーダーやコツは?時間足りない場合は?練習問題付き」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
表の空欄の推測(20時間)
表の空欄の推測は玉手箱の科目の中で一番難しいので、一番多くの勉強時間を確保しても問題ありません。
※表の空欄の推測は上記でご紹介したので、ここでは割愛させていただきます。
表の空欄の推測では以下7パターンの問題が出題されるので、まずはこれらを頭に入れることから始めましょう。
- 比例
- 大小
- 算出式
- 推移
- 合計が同じ
- 積算
- 列ごとに計算
そして、練習問題を解く際には以下2つのポイントを意識してください。
- 空欄の項目と連動する項目を見つける
- 計算しやすい数値を使う
それぞれの詳細は「玉手箱:表の空欄の推測とは?できない人続出!何割必要?導入企業は?難しいのでコツが必要です」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
模擬試験(4時間)
最後は模擬試験で玉手箱の総仕上げを行いましょう。
多くの玉手箱の問題集には巻末に模擬試験が掲載されているので、それを活用すれば問題ありません。
※「玉手箱の模擬試験(模試)を受けれるサイト3つと全問題集をご紹介」もぜひ参考にしてください。
模擬試験を行う際には必ず時間を測りましょう。
上記でも解説した通り、玉手箱は問題数に対して試験時間がかなり短いWEBテスト(適性検査)なので、時間を気にせずに解いてしまうと対策になりません。
※「玉手箱とWEBテスト・適性検査の違いとは?対策方法や例題・問題集もご紹介!」もぜひ参考にしてください。
そして、間違えた問題は必ず解答・解説を読んで復習しましょう。
間違えた問題をそのまま放置してしまうと、問題を解いた意味がありません。
問題の解法を頭に入れるまでが1セットです。ただ単に問題を解くだけの勉強は時間の浪費でしかないので絶対にやめましょう。
玉手箱の勉強時間が60時間も取れない人は3時間または1週間でもOK
学校や仕事で忙しい就活生・転職活動中の社会人の中には、60時間も玉手箱の勉強に使えないという人もいるでしょう。
そんな人のために、「玉手箱対策は1週間で可能!具体的スケジュールを大公開」という記事もご用意しているので、気になる人はぜひご覧ください。
1日2時間 玉手箱の勉強をした場合、1週間だとトータルで14時間です。
もちろん1週間(14時間)よりも60時間の方が圧倒的に勉強時間が長いので、後者の方がより重点的な対策が可能ですが、人によっては1週間でも点数を上げることは十分に可能です。
もっと言うと、玉手箱にはたった3時間の勉強で玉手箱が通過してしまう勉強法があります。
これさえあれば1週間も勉強することなく、限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。
これは私が100回以上もの玉手箱受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。