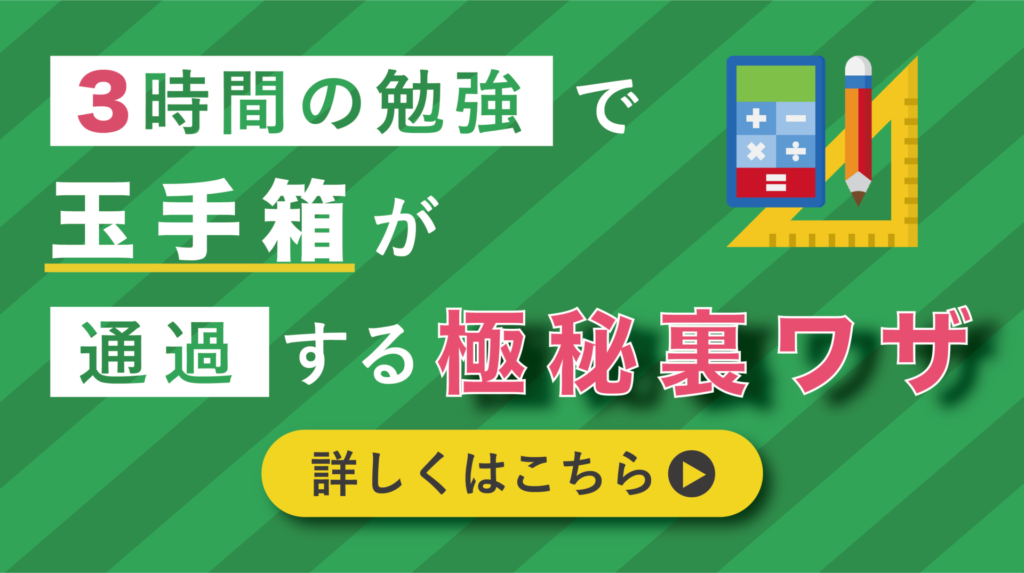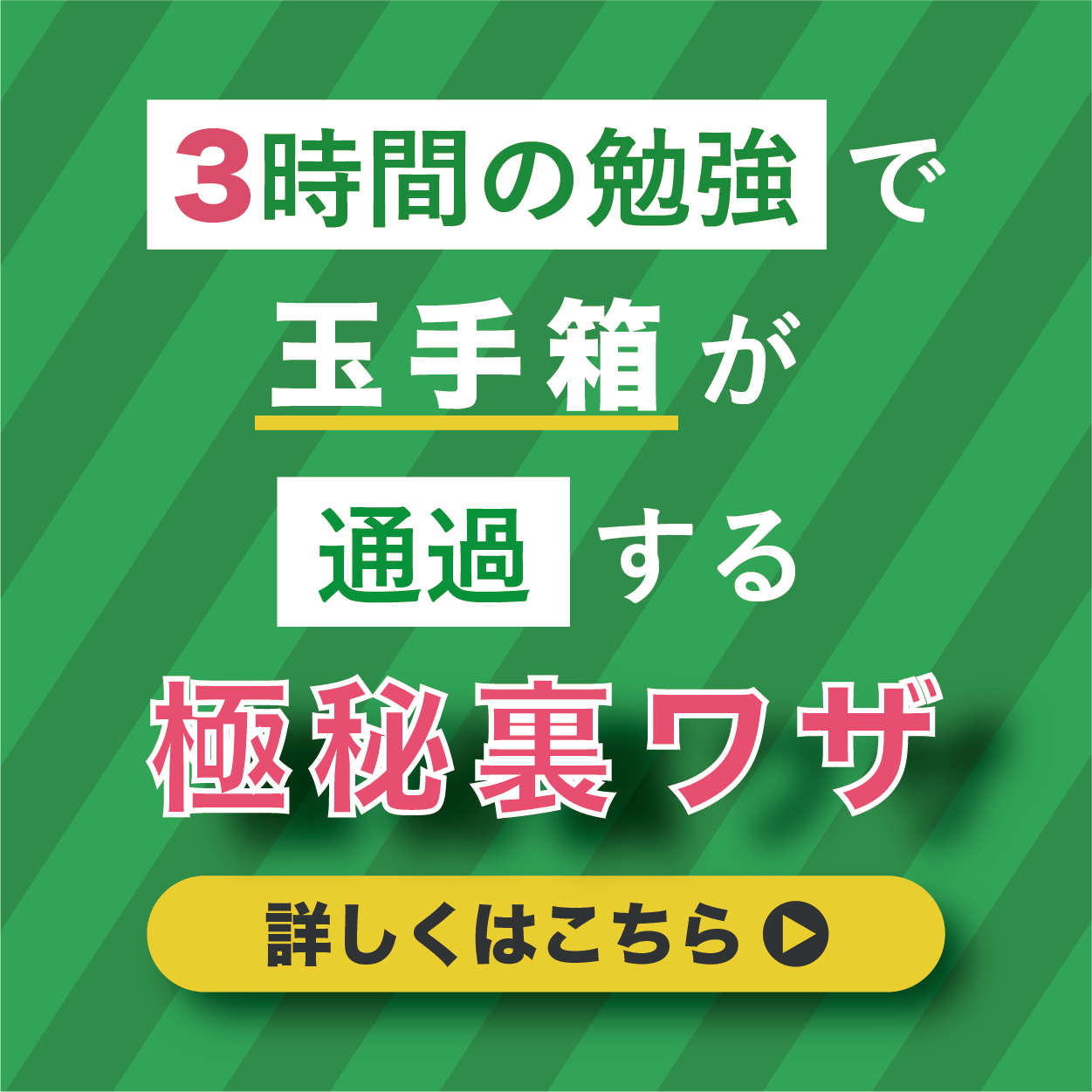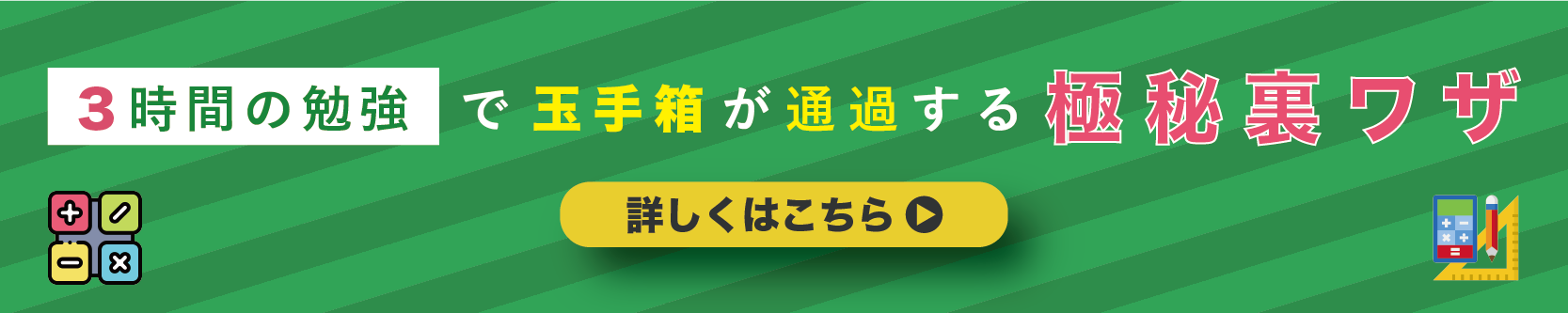WEBテスト(適性検査)の一種である玉手箱の言語では論理的読解が出題される可能性が高いです。
※「玉手箱の言語のコツは?練習問題・解答も!おかしい・難しいという声もご紹介」もぜひ参考にしてください。
論理的読解は長文読解の1つで、難易度は高めです。
本記事では玉手箱の受検回数=100回以上・日本一玉手箱に詳しい私アキラが、玉手箱の論理的読解とはどんな問題なのかについて具体例で解説した後、解き方のコツもご紹介します。
最後には論理的読解の練習問題もご用意しています。玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人はぜひ解いてみてください。
ちなみにですが、玉手箱にはたった3時間の勉強で玉手箱が通過してしまう勉強法があります。
これさえあれば限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。
これは私が100回以上もの玉手箱受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。
目次
玉手箱の論理的読解とは?どんな問題?
玉手箱の言語で出題される論理的読解は与えられた長文を読み、設問文が論理的に正しいかどうかを判断する問題です。「GAB形式の言語」と呼ばれることもあります。
※「玉手箱形式とは?GAB形式・IMAGES形式との違いは?例題で解説」もぜひ参考にしてください。
論理的読解は玉手箱の言語の中で、最も多くの企業が導入しているのが特徴です。
長文の文字数は600文字程度で、テーマは人文系や自然科学系、エッセーなど様々です。
1つの長文につき4つの問題が用意されており、問題数と試験時間は
- 32問で15分
- 52問で25分
のいずれかです。試験時間がかなりタイトなのでご注意ください。
※「玉手箱の所要・試験時間と問題数を科目別に解説!サンプル問題付き」もぜひ合わせてご覧ください。
論理的読解の例題は以下の通りです。
【例題】
次の文章を読み、各設問文についてA、B、Cのいずれかにあたるか答えなさい。
「デザイン」っていったい何だろう。この単刀直入な疑問あるいは質問に、即座にひとつの答えを出すことは、 なかなか大変なことだ。家具や衣服あるは書物など、人間がつくりだすさまざまなものは、その良し悪しは別にしてすべてデザインされている。そして、すべてのものがわたしたちの生活に関わってている。だから生活っていったい何だろうという質問と同じほどに、 デザインって何だろうという問いに対して答えをすぐに出すことが難しいように思える。
けれども、 ここでは「デザインとは何か」 という問題について、いくつかの目を向けるべき要素をあげながら、できるだけ簡単な道筋で考えてみたい。
わたしたちの生活と同じように、デザインもまた、多様な要素の複合的な関係の中で、成り立っているといえる。つまり、社会や経済や技術や産業あるいは人々の思考や感覚などの複合的な関係の中でデザインは生まれてくる。
そのデザインをプランドやデザイナーに関する蘊蓄(うんちく)ではなく、 もう少しだけ踏み込んで、デザインそのものについて目を向けてみよう。
まず第一に、わたしたちが何かをデザインするには、要因あるいは動機づけとして何かがあるはずだ。その要因はいくつかあるだろうが、そのひとつに「心地良さ」を求めるということがある。
第二に、 デザインは、わたしたちが自然や道具や装置に関わり、それを手なずけていく一連の計画と実践だといえるだろう。もちろん、 そこには技術の変化も関わってくる。
第三に、デザインは趣味や美意識と関わっている。
第四に、近代以前において、とりわけ顕著に見られることだが、デザインは地域や職業や階級の違いと結びつき、それらを表象するものとされてきた。デザインには社会的な規範が関わっていると見ることもできる。
出典:柏木博『デザインの教科書』講談社現代新書
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)デザインをする際にもっとも重要な動機づけは「心地良さ」である。
(2)生活は多くの要素の複合的な関係の中で成り立っている。
(3)近現代のデザインは職業や階級の違いと結びつくことはなくなった。
(4)ブランドやデザイナーの価値は、もっとも結びつきの強い職業や階級によって左右される。
【解答&解説】
(1)正解はBです。本文には「その要因はいくつかあるだろうが、そのひとつに「心地良さ」を求めるということがある」とあり、「もっとも重要な動機づけは心地良さ」とは書いていません。
「心地良さ」は動機づけのひとつです。
(2)正解はAです。本文に「わたしたちの生活と同じように、デザインもまた、多様な要素の複合的な関係の中で、成り立っているといえる」とあることから、正しいと言えます。
(3)正解はBです。最後の段落に「近代以前においてとりわけ顕著に見られる」と書いていますが、近現代にはなくなったとは書かれていません。
(4)正解はCです。価値に関しての言及は本文には一切ありません。ブランドのイメージなど、既存の知識に引っ張られないように注意しましょう。
【玉手箱】論理的読解のコツは?
玉手箱の論理的読解のコツは以下の3つです。
- 選択肢A〜Cの意味を事前に理解しておく
- 設問文を先に読む癖を付ける
- 時間を意識しながらわからない問題は勘で回答する
それぞれ詳しく解説していきます。
※「玉手箱のコツ・攻略法は?解き方のポイントを科目別に解説!」もぜひ参考にしてください。
選択肢A〜Cの意味を事前に理解しておく
論理的読解では上記でご紹介した選択肢A〜Cがすべての問題で用意されています。
なので、玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人はあらかじめ選択肢A〜Cの意味を頭の中に入れておきましょう。
試験が開始されてから選択肢A〜Cを見て、その意味を理解するのは時間の無駄です。
選択肢A〜Cはもう少し噛み砕いて説明すると、以下のようになります。
- A=本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。
- B=本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。
- C=本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。
設問文を先に読む癖を付ける
玉手箱の論理的読解では、単純計算すると1つ長文(4問)にかけられる時間は2分弱です。
本文を読んだ後に設問文を見て問題を解くと確実に時間オーバーします。
なので、先に設問文を読み、正誤の判断に関係がありそうな部分のあたりをつけながら本文をざっと読むことをおすすめします。
時間を意識しながらわからない問題は勘で回答する
繰り返しにはなりますが、玉手箱の論理的読解は試験時間がかなりタイトなので、わからない問題にいつまでも時間を使うことはできません。
※「玉手箱が解き終わらない・全部解けない人がやるべきことは?計数・英語・四則逆算など科目別に解説」もぜひ参考にしてください。
ときにはわからない問題はさっさと切り捨て、次の問題に移る勇気も必要です。
玉手箱は誤謬率が計測されないWEBテスト(適性検査)です。つまり、正解数のみをもとにして採点が行われます。
※詳しくは「玉手箱で誤謬率は計測されない!わからない問題は適当に埋めるでOK!」をご覧ください。
なので、論理的読解でわからない問題や判断に迷う問題はさっさと勘で回答して次の問題に移りましょう。
論理的読解は選択肢がA〜Cの3つしか用意されていないので、勘で回答したとしても約33%の確率で正解することができます。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
論理的読解の選択肢BとCの違いは?
玉手箱の論理的読解を解いていると、選択肢BとCの判断に迷うケースが多々あるかと思います。
まず前提として、論理的読解で問われる「論理的に正しいかどうか」は本文の内容に基づいて判断しなければなりません。
一般常識や自分の主観・意見をもとに判断するのは絶対にNGです。
本文の内容が一般常識とは言えないものであっても、設問文が本文の論理に沿っていればAが正解となります。
その上での選択肢BとCの違いですが、Cは設問文の内容が本文では述べられていないときに使用します。
例えば、上記でご紹介した例題の(4)の正解はCですが、これは価値に関しての言及が本文には一切ないからです。
もし価値に関しての言及が本文にある上で設問文の内容が本文と異なる場合はBが正解となります。
Bは設問文の内容に本文と食い違いがあるときに選択します。
BとCで判断に迷いが出るときは、設問文の内容が本文で述べられているかをチェックしてください。
※「玉手箱の論理的に導けないとは?選択肢BとCの違いは?例題で解説!」もぜひ合わせてご覧ください。
【玉手箱】論理的読解の練習問題
最後に論理的読解の練習問題をご用意しました。
本番の玉手箱で出題される問題の難易度に近い練習問題なので、玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人はぜひ解いてみてください。
【練習問題1】
次の文章を読み、各設問文についてA、B、Cのいずれかにあたるか答えなさい。
今日のように激動が常態化してしまった時代、将来を予測して行動するということはどの国にとっても難事になっている。ということは一方では、遅れてスタートしたのだが一周過ぎていたらトップに立っていた、などという事態も珍らしくなくなるということでもある。これが現情ならば、激動している情況に浮足立ったあげくの拙速くらい、害をおよぼすこともないのではないか。
ただし、「動けない」のではなくて「動かない」のだから、「冬眠」ではなくて「静観」であるのはもちろんだ。それゆえに「動かない」間も「動く」ときにそなえて冷徹な観察を怠ってはならないのは言うを待たないくらいに当り前で、当事者にとっての仕事は減るどころか増えるくらいでないと、この政略(ストラテジー)の成果は望めなくなる。
そしてここではじめて、「説明責任」の必要が出てくる。なぜ今は動かないほうが適策かを、有権者に向って説明する必要があるからだ。だが、なぜか説明責任という言葉は、「これこれこういう理由でやりました」という場合にしか使われないようであるのは、説明責任(アカウンタビリティ)の意味するところの半分でしかない。「これこれこういう理由で、今のところはやりません」という使い方もあるべきで、言い換えれば、「これこれこういう理由で、今年度の成果は出せません」という場合の説明責任である。そして上司は、その理由に説得性があると認めれば、成果が今のところは出せないということも、「成果」として認めるべきではないだろうか。
出典:塩野七生『日本人へ リーダー篇』文春新書
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)将来を予測して行動することが難しくなっているのは、情況の激動が常態化しているからである。
(2)「動かない」ことを成果として認められるには、当事者にとっての仕事は「動く」ときよりも増えていなければならない。
(3)激動する情況においては、「動かない」方が成果を望める。
(4)「説明責任」という言葉は「動かない」ことへの説明に対しても使われるべきである。
【解答&解説】
(1)正解はAです。冒頭にある「今日のように激動が常態化してしまった時代、将来を予測して行動するということはどの国にとっても難事になっている」から正しいと言えます。
(2)正解はCです。本文に「当事者にとっての仕事は減るどころか増えるくらいでないと、この政略(ストラテジー)の成果は望めなくなる」とありますが、「動かなくても(仕事が増えるくらい)観察が必要」とは書かれていません。
つまり、増えることの必然性を問う記述は本文中には存在せず、判断できません。
(3)正解はBです。本文に「激動している情況に浮足立ったあげくの拙速くらい、害をおよぼすこともないのではないか」とあるものの、「動かない方が成果を望める」と断言するのは誤りです。
「動く」「動かない」ことも比較していません。
(4)正解はAです。本文に「なぜか説明責任という言葉は・・・という場合の説明責任である。」とあります。後半の趣旨となる部分であり、正しいことがわかります。
【練習問題2】
次の文章を読み、各設問文についてA、B、Cのいずれかにあたるか答えなさい。
西欧の遠近法や明暗法は、 ちょうどある位置でカメラを構えてシャッターを切った時のように、画家の視点は一定の場所に固定されていて、対象も変化のない一定不変の状態にあるということが、基本的前提になっている。画家と対象との距離の差を画面における形態の大小や色彩の鮮明度に翻訳して表現するのが遠近法であり、対象に対する光のあたり方を陰影によって表現するのが明暗法だからである。例えば、人物を描く場合、画家により近い場所に位置する人物は画面ではいっそう大きく、衣裳などの色彩もいっそう鮮明に表現され、画家より遠い場所にいる人物は、それだけ小さく、 また空気の層の作用によって色彩も不鮮明に描かれる。逆に言えば、画面である人物が大きく描かれているとしても、それはその人物が画家により近い所にいるということを示すのであって特にその人物が背が高いということを表わすものではないし、同様に、不鮮明な色彩は距離がいっそう離れていることを表わすものであって、衣裳が汚れていることを表現しようとしているわけではない。だが、画家と対象との距離というものは、当然のことながら、画家の位置が変わればそれに応じて変わる。もし画家が人物を描くたびに、つねにそのすぐそばまで移動して描いたとしたら、遠近法は成立しないであろう。その代り、画中の人物は、つねに同じ大きさで鮮明に描き出されるということになる。洛中洛外図において日本の画家が行なったのは、まさにそのようなことである。画家は町のなかを自由に動き廻って、さまざまの場所を観察し、店先の様子や人びとの姿などをいわば至近距離から眺めて、それぞれの部分を次つぎと画面の上に並べていった。つまり洛中洛外図は、ひとつの固定した視点から眺められた都市図ではなく、都市のさまざまの部分を、つまり複数の視点による都市の姿を画面の上に並置したものなのである。そのそれぞれの部分は、いずれも、例えば人物たちの顔かたちや衣裳の模様まではっきりとわかるように鮮明に描かれているので、相互のあいだに距離感の差はなく、全体として画面は平面的な拡がりを見せることとなる。
出典:高階秀爾『増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い』 岩波現代文庫
A:文脈の論理から明らかに正しい。または正しい内容を含んでいる。
B:文脈の論理から明らかに間違っている。または間違った内容を含んでいる。
C:問題文の内容だけからでは、設問文は論理的に導けない。
(1)洛中洛外図において日本の画家は、対象との距離の差を画面における形態の大小や色彩の鮮明度に翻訳して表現した。
(2)洛中洛外図では、当時の人物たちの生活を余すことなく表現するために同じ大きさ、鮮明さで表現した。
(3)当時の日本には遠近法という概念が存在しないため、洛中洛外図のように平面的な拡がりの絵を描いた。
(4)洛中洛外図は複数の視点からみた都市の姿を描いた作品である。
【解答&解説】
(1)正解はBです。設問ぶんの内容は西欧の画家が採った手法の「遠近法と明暗法」の説明です。
(2)正解はCです。本文に「当時の人物たちの生活を余すことなく表現するため」という記述はありません。
(3)正解はCです。日本に西欧の遠近法が広まったのは江戸後期です。『洛中洛外図屏風』は16世紀初頭から江戸時代にかけて制作されており、それ以前の作品ではありますが、文中にはその記述はありません。
(4)正解はAです。文中に「洛中洛外図は、ひとつの固定した視点から眺められた都市図ではなく、都市のさまざまの部分を、つまり複数の視点による都市の姿を画面の上に並置したもの」と記述があります。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
今回は玉手箱の論理的読解を取り上げました。
論理的読解は事前にしっかりと対策をしておかないと高得点を取ることは難しいので、早めの対策を心がけましょう。