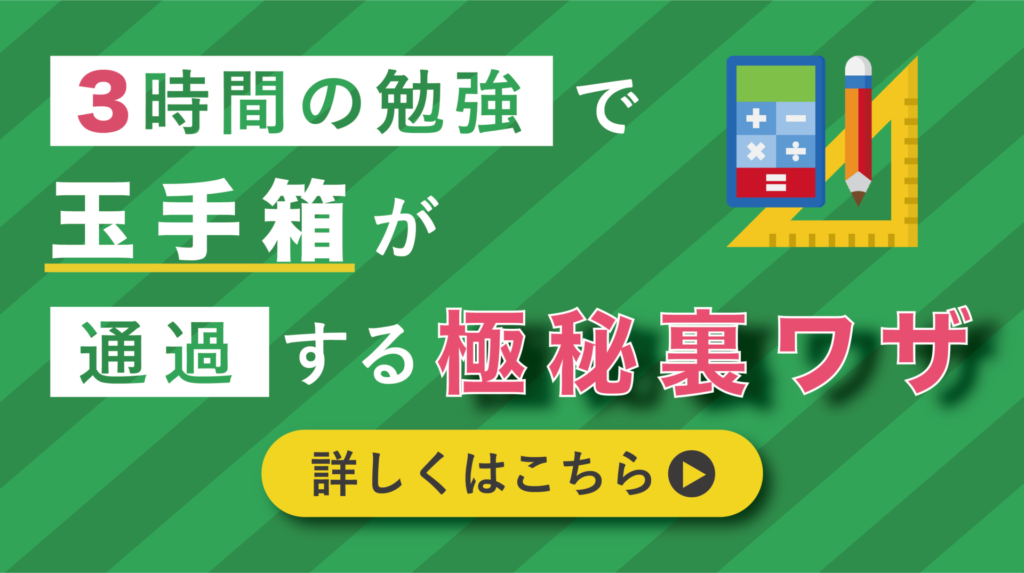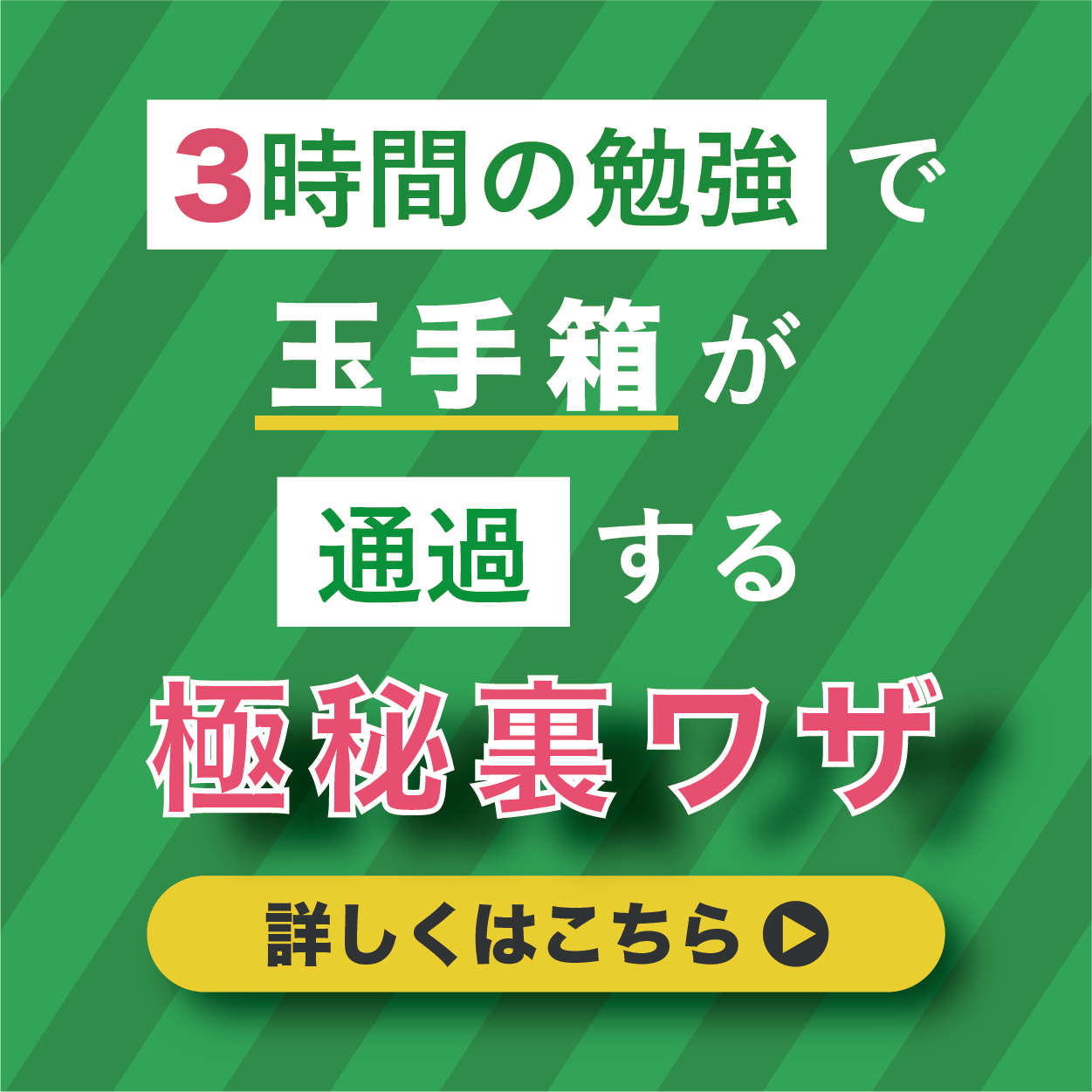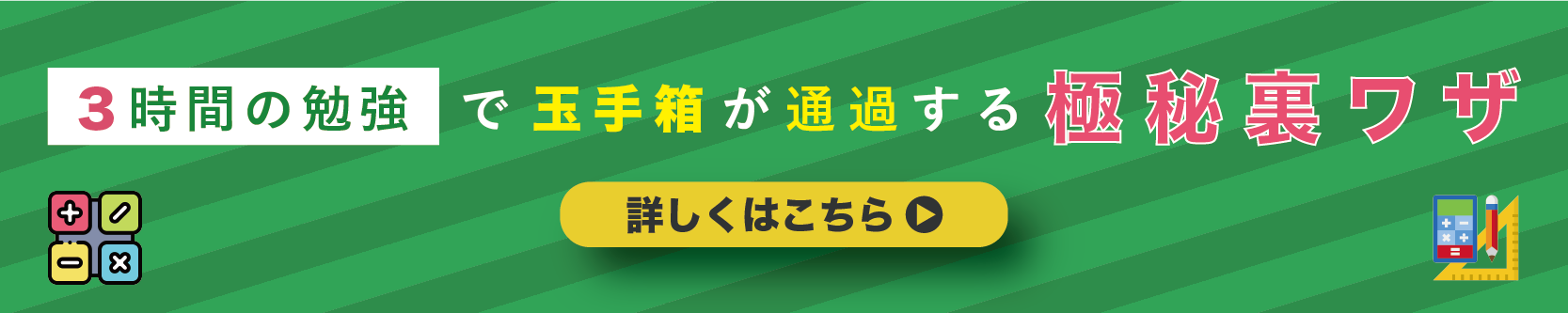玉手箱の言語では趣旨判定という問題が用意されています。
※「玉手箱の言語のコツは?練習問題・解答も!おかしい・難しいという声もご紹介」もぜひ参考にしてください。
後ほど詳しく解説しますが、趣旨判定は用意された文章の趣旨を回答する問題です。
難易度はそこまで高くありませんが、油断せずにしっかりと対策しておきましょう。
本記事では玉手箱の受検回数=100回超・玉手箱マスターの私アキラが、趣旨把握の例題やコツについて解説していきます。また、玉手箱の趣旨把握という科目との違いも取り上げます。
最後には練習問題も用意しているので、ぜひ最後までお読みください。
ちなみにですが、玉手箱にはたった3時間の勉強で玉手箱が通過してしまう勉強法があります。
これさえあれば限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。
これは私が100回以上もの玉手箱受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。
玉手箱の趣旨判定とは?例題で解説
玉手箱の言語で出題される趣旨判定は提示された長文に関する4つの設問をA・B・Cに振り分ける問題です。
A・B・Cは以下の通りです。
A:筆者の趣旨(もっとも伝えたいこと)が述べられている。
B:筆者はそのことに触れているが、趣旨ではない。
C:この文章とは関係ないことが述べられている。
趣旨判定は趣旨判断またはIMAGES形式とも呼ばれています。例題は以下です。
※「玉手箱の問題・例題を全科目紹介!練習問題も無料!どんな問題か知りたい人必見」もぜひ参考にしてください。
【例題】
次の文章を読み、続く設問文についてそれぞれA、B、Cを判断して選びなさい。ただし、4つの設問文の中には、AとCにあてはまるものがいずれも1つ以上含まれています。
新入社員であれ何年かビジネスの経験を積んだ人材であれ、誰もが強く望むのが、能力を高めながら自らの願いを叶えていくことです。高収入、業界での高い評価、やりたい仕事に就くなど、ほしいものは人それぞれでしよう。では、それを手に入れるために役立つスキルとは、具体的にどんなものでしようか。
少し考えただけでも、IT関係のスキルや業界の知識、業務に関連した資格など、たくさんの例があがってくるでしよう。語学などは、グローバル化を遂げた企業で必要となるシチュエーションが数多くありそうです。またOA機器を使いこなす能力や、仕事に関連した資格などがあれば、業務をスムーズにこなせたり、会社からの評価が上がったりするかもしれません。このやり方でもいいのですが、じつはもっと業務に必要でスキルアップに役立つ能力があるのです。
部下を従えて業務をこなしたことがない人がイメージするスキルは、前述のようなものが多いようです。しかし管理職や経営者などの評価を下す立場の人問が望む能力は、まったく違うところにあります。それは自ら課題を見つけ、それを解決していく「考える力」なのです。
たとえば、日々の業務のなかで困ったことがあったり、こうしたら効率アップできるというようなアイデアを思いついたりしたとします。それを、こなすべき業務のほかに解決すべき課題とし、改善案を考えたり、企画書にまとめたりすることが、企業の業務改善につながっていくのです。この小さな改善の積み重ねで中小企業が大企業へと発展した例は、枚挙に暇がありません。
課題を見つけ解決していく能力は、直属の上司などにしか評価されないものと思われがちですが、ビジネスで成功を収めてきた人の多くは、 この力が優れています。新卒の就職活動や転職の面接などでも、見られているのはじつは、こういった発想力や前向きに業務をこなす積極性なのです。
出典:『いちばんわかる!Webテスト 玉手箱』高橋書店
A:筆者の趣旨(もっとも伝えたいこと)が述べられている。
B:筆者はそのことに触れているが、趣旨ではない。
C:この文章とは関係ないことが述べられている。
(1)課題を見つけて解決していく能力はビジネスで成功を収めてきた人の必須スキルである。
(2)人材に求められるスキルとは、課題を見つけて解決していく能力である。
(3)語学やOA機器を使いこなす能力よりも課題を見つけて解決していく能力の方が評価される。
(4)会社からの評価を獲得するためには、問題解決能力が必須である。
【解答&解説】
(1)正解はCです。設問文に記載の能力が「必須スキル」であるとは本文には書かれていません。
(2)正解はAです。
(3)正解はBです。第2段落第3段落で設問文の内容が書かれていますが、この文章の趣旨ではありません。
(4)正解はCです。本文に設問文の記載は一切ありません。
【玉手箱】趣旨判定の試験時間・問題数は?
趣旨判定の試験時間・問題数は10分・32問です。
※「玉手箱の所要・試験時間と問題数を科目別に解説!サンプル問題付き」もぜひ参考にしてください。
1つの長文につき4つの設問が用意されているので、全部で8つの長文が出題されます。
全問を解ききるには、1問あたり約18秒ペースで解かなければなりません。
具体的な時間配分としては、長文を45秒で読み、残り30秒で4つの設問に回答するペースを目指すのが良いでしょう(75秒×8長文=10分)
趣旨判定で出題される長文は就活やキャリア関係のものが多く、内容自体は難解ではありません。
日頃から文章を読むことに慣れていれば比較的スラスラと読めるでしょう。
ちなみにですが、玉手箱は正解数をもとにして採点が行われます。不正解の数は点数に影響を及ぼしません。
※詳しくは「玉手箱で誤謬率は計測されない!わからない問題は適当に埋めるでOK!」をご覧ください。
上記の通り趣旨判定は試験時間がかなりタイトなので、判断に迷う設問があったときは時間をかけずにさっさと勘で回答して次の設問に進みましょう。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
【玉手箱】趣旨判定のコツは?
玉手箱で出題される趣旨判定では以下の記載があります。
4つの設問文の中には、AとCにあてはまるものがいずれも1つ以上含まれています。
文章の趣旨は1つなので、1つの長文における4つの設問のうちAが答えとなるものは必ず1つです。
なので、趣旨判定は以下の手順で解くとスムーズに回答できます。
- 長文の内容の大枠を捉えながら読む
- 比較的見つけやすいAとCが答えになる設問を探す(Aが答えとなるものは必ず1つ・Cが答えとなるものは最低1つある)
- 残った設問をBかCに振り分ける
また、長文を読むときは文末表現に注目しながら読むのもポイントです。
- 「〇〇だ」「〇〇である」などの断定表現
- 「〇〇だが」「しかし」などの逆接表現の後の文
には筆者の主張や趣旨が記載されていることが多いので、この2つには特に注目するようにしましょう。
趣旨判定と趣旨把握の違いは?
玉手箱の言語では趣旨判定の他に趣旨把握という科目も用意されています。
※「玉手箱の種類・パターン12個の内容をすべてご紹介!よくある組み合わせは?」もぜひ参考にしてください。
科目名が似ていますが、出題される問題内容は異なるのでご注意ください。
趣旨把握は提示された長文の趣旨(=筆者の訴えに最も近いもの)を4つの選択肢から選ぶ問題です。
1つの長文に対して設問は1つのみです。
しかし、近年は趣旨把握を出題する企業がほとんどないので、対策の優先度はかなり低いです。
趣旨把握の例題は以下です。
【趣旨把握の例題】
次の文章を読んで、筆者の訴えに最も近いものを4つの選択肢の中から1つ選びなさい。
ディベート能力はいかにしたら身につくのであろうか。最近では、日本でも小・中学校間でのディベート大会なるものが実施され、それなりの成果を挙げているようだが、それは一部の学校だけであり、多くの学生はディベート能力を培っていない。そのチャンスがないのである。
私が欧米社会に行って、すばらしいな!といつも感じるのは、子供がまだ3〜4歳の頃から、親は何か事があると、「君はそれについてどう考えるの?」というように、考えることを促す努力をしていることである。子供は必死で言葉を選びながら、「僕はね、僕はえーとえーと、こう思うの」と、真剣に語ろうとしている。そうした日常生活での積み重ねが一人ひとりの主体的考えを育てていくのである。
しかし、日本では、「〇〇ちゃんこれはこうですよ!」と、親の価値観、それもその前から受け継いだ価値観に基づく意見を断片的に、そして一方的に押し付けているケースが多い。これではディベート能力の前提として持つべき主体的考えが培われない。
この意味からも、これからはもっと子供たちが自分のことを表現する場を設けるべきである。私は長年、「小学生の時から卒業論文を書かせよ」ということを主張してきたが、それはこうした思いからである。
出典:『Webテスト最強問題集』大和書房
- ディベート能力は生まれながらに身についているものだから、それを鍛えればよい。
- 全ての日本の親は子供に質間し、それを真面目にとらえて考えることを促している。
- ディベート能力を身につけるには、子供が自己表現をする場を増やすことが必要だ。
- 小学生には作文のほか、生活で感じたことをまとめる卒業論文が必要だ。
【解答&解説】
正解は3・・・(答)です。その他の選択肢の詳細を見ていきましょう。
1=本文に「ディベート能力は生まれながらに身についているもの」とは書かれていません。
2=「子供に質間し、それを真面目にとらえて考えることを促している」のは日本ではなく欧米です。
4=本文で作文の必要性については記載がありません。また、卒業論文の内容についても「生活で感じたことをまとめる」とは書かれていません。
【玉手箱】趣旨判定の練習問題
最後に趣旨判定の練習問題をご用意しました。
本番の玉手箱で出題される問題に近い難易度の練習問題なので、玉手箱を受検予定の就活生や転職活動中の社会人はぜひ解いてみてください。
【練習問題】
次の文章を読み、続く設問文についてそれぞれA、B、Cを判断して選びなさい。ただし、4つの設問文の中には、AとCにあてはまるものがいずれも1つ以上含まれています。
面接の間、面接官の話を聞かず、自分の主張を押し通す人も「できない人」だ。話の途中で、口を挟み、回答をしてしまう。
コミュニケーション能力は、話す力以上に、聞く力が重要になる。話を聞けない相手に対して、親身に話をしようとは思わない。話を聞けない人は、必然的に周囲の協力を得られず、いずれは組織内で孤立してしまうだろう。
話し下手は、その場で相手が判断できるので、トレーニングを積むことで一定の進歩があるが、話を聞けない人は、どれだけ理解しているのかなかなかつかめず、話を聞けるようになるまで、時間を要する。
面接官が説明している途中で、「わかった」と理解した様子を示しても、話を聞けない応募者は、説明したことに対して再度、質問をする。話を聞けないため、理解力が劣り、教育に時間を要することも多い。
幼少時から、いつも注意をされてきた経験が積み重なり、話を聞けなくなることもある。注意や叱られることに対して、拒否反応を示し、受け入れようとしないため、一見わかった振りをしていても、実は理解しておらず、ビジネスではトラブルを起こす。
我が強いとも言えるが、つまりはコミュニーケーション能力がないので、相手は不愉快な思いをする。こういった人は、 ビジネス上では、仕方がないではすまされず、信頼関係を築けないことが多いため、会社の大きな損失になりかねない。
出典:谷所健一郎『「できる人」「できない人」を見抜く面接術』
A:筆者の趣旨(もっとも伝えたいこと)が述べられている。
B:筆者はそのことに触れているが、趣旨ではない。
C:この文章とは関係ないことが述べられている。
(1)話し下手はトレーニング次第で改善できるが、聞き下手は改善に時間を要する。
(2)幼少期から注意をされ続けると話を聞けない人になることがある。
(3)話を聞けない人は、ビジネスにおいて信頼関係を築けずに会社の損失になる。
(4)聞き上手になるためには、相手の話を親身に聞くことが重要だ。
【解答&解説】
(1)正解はBです。設問文は第3段落の要約ですが、本文の趣旨ではありません。
(2)正解はBです。第5段落に「幼少時から、いつも注意をされてきた経験が積み重なり、話を聞けなくなることもある」とありますが、本文の趣旨ではありません。
(3)正解はAです。
(4)正解はCです。本文ではコミュニケーションについて話す力と聞く力の論を展開していますが、聞き上手になるための方法は記載されていません。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
今回は玉手箱の趣旨判定の例題やコツを取り上げました。
趣旨判定は玉手箱の科目の中では易しい方なので、得点源にできるようしっかり対策しておきましょう。